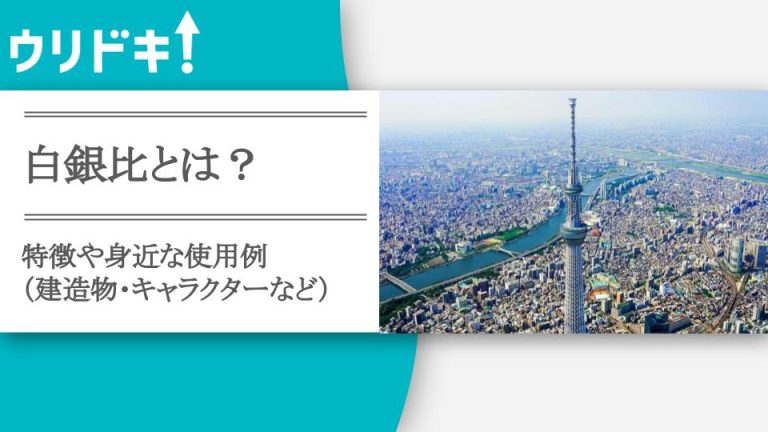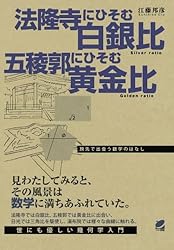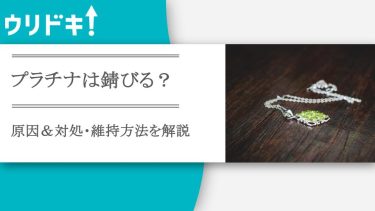- 白銀比の言葉の意味が分かる
- 実際に白銀比が用いられている例が分かる
- 白銀比が好まれる理由が分かる
この記事では、白銀比の概要や白銀比を用いた具体例などについて解説します。
似た言葉である「黄金比」について聞いたことがある方は多くいるでしょう。しかし、白銀比については一般的にはあまり知られていないかもしれません。
白銀比は、古くから日本の優れたデザインに採用されている比率で、美術などの製作だけでなく、製品開発などにも役立つ考え方です。
白銀比について詳しく解説した書籍なども紹介するので、「白銀比についてもっと知りたい」「デザインなどに活用したい」という方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
白銀比とは
白銀比とは、建築物やデザインにおいて人間が見たときに美しさや安定感を感じやすい比率を表す言葉で、貴金属比の一種です。
白銀比の比率は約1:1.414もしくは5:7とされています。白銀比は、特に古くから日本人に好まれる比率です。そのため、世界的なデザインより、日本国内の優れたデザインや製品に多く採用されています。
貴金属比には、白銀比のように各貴金属の名前がついており、ほかの貴金属比としては黄金比、青銅比などが有名です。
もう1つの白銀比「第2貴金属比」について
白銀比には2種類あります。そのうち、「白銀比とは」で紹介した比率は「大和比」と呼ばれる比率です。もうひとつは「第2貴金属比」と呼ばれており、周期表で白銀が黄金に続く第2の貴金属であることに由来しています。
同じ白銀比に分類されているものの、両者は比率が若干異なり、大和比が約1:1.414(5:7)であることに対し、第2貴金属比は1:2.414(5:12)です。
白銀比が用いられている例
白銀比は、古くから日本国内のさまざまな分野で活用されています。ここでは、実際に白銀比が用いられている例を具体的に見ていきましょう。有名な建築物から生活に浸透している身近な例まで、意外なところにも白銀比が使われていますよ。
用紙規格
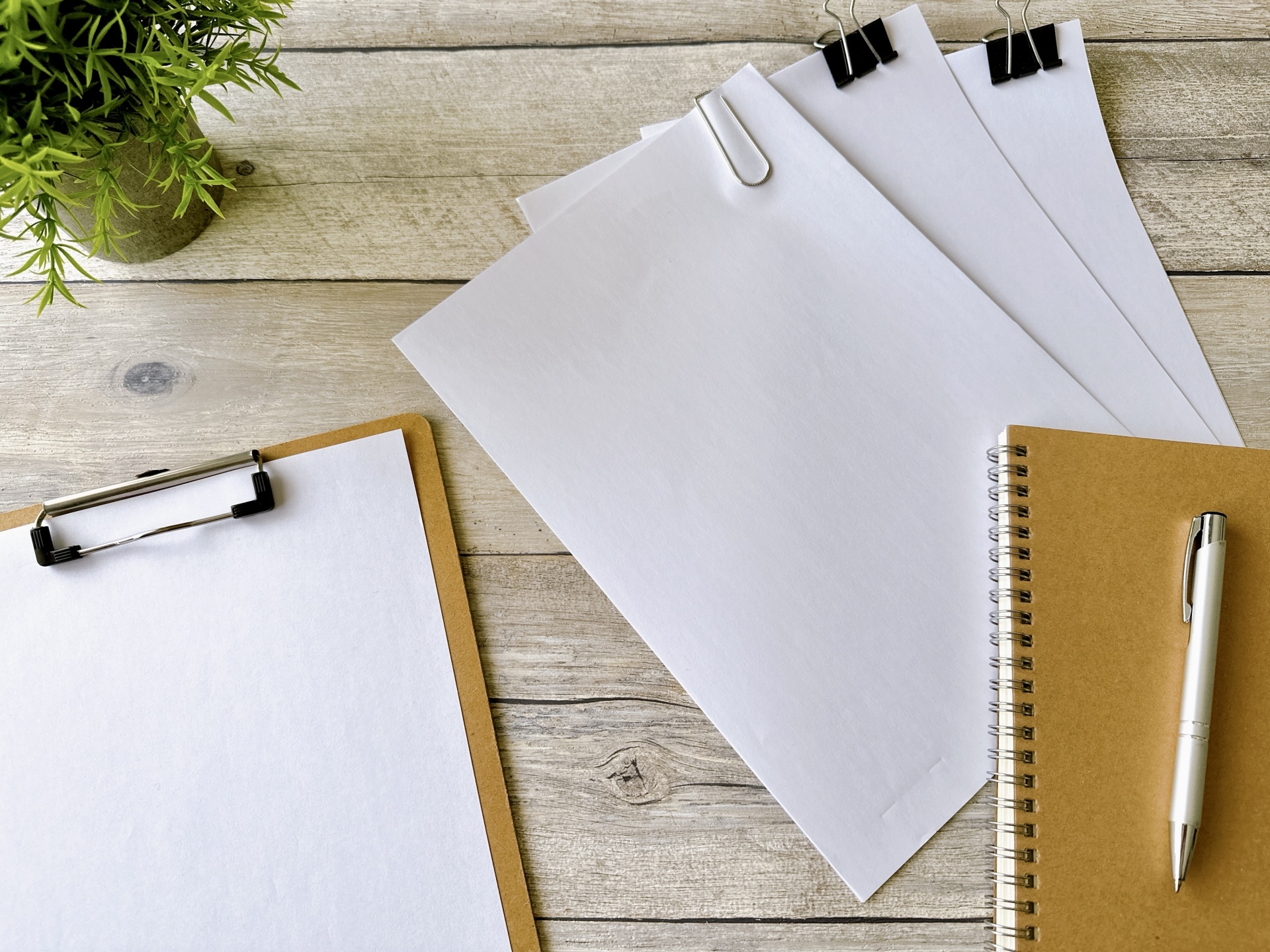
A判とB判はいずれも同じ白銀比が採用されているものの、それぞれルーツが異なります。A判はドイツ、B判は日本で江戸時代に使われていた美濃判がルーツです。
建造物
法隆寺

法隆寺では、「金堂」と「五重塔」に白銀比が採用されています。金堂は1階部分と2階部分の屋根の幅、五重塔は1階部分と最上階の屋根の幅が白銀比です。
銀閣寺

銀閣寺では、1階部分と2階部分の屋根の幅の比率に白銀比が採用されています。
伊勢神宮

伊勢神宮は建築物の数が多く、特定の建築物の名前が挙がることはありませんが、白銀比が用いられていることで有名です。
東京スカイツリー

幅同士や縦横の比率ではなく、「第二展望台までの高さ」と「全体の高さ」という、高さ同士に白銀比を採用している例です。
キャラクター
日本国内で愛されている多数のキャラクターにも、白銀比が採用されています。
- ドラえもん
- アンパンマン
- ハローキティ
- トトロ
- スヌーピー
いずれも、大人から子どもまで幅広く親しまれているキャラクターばかりですね。
ほとんどは国内で生まれたキャラクターです。一方で、スヌーピーのように海外から来たキャラクターのなかにも白銀比が採用されている場合があります。
白銀比の与える印象
白銀比が人に与える印象としては、「かわいらしい」「親しみやすい」といった印象があります。
たとえば、白銀比をあるデザインの縦と横のサイズに採用した場合、黄金比よりも比率が小さく、見た目は小振りです。キャラクターにあてはめると「頭が大きく等身が低い」と表現できます。
そのため、白銀比を見るとかわいらしく親しみやすい印象を抱きやすいのです。
白銀比は日本人が好きな比率?
白銀比は、特に日本人が好む比率として知られています。実際、日本で古くから採用されている貴金属比の多くは白銀比です。
日本で白銀比が好まれる理由のひとつは、日本人特有の美意識にあると言われています。日本人は、一般的にスタイリッシュでかっこいいものよりも、かわいらしいものを好むため、白銀比を心地よく感じやすいのです。
一方、建築物など、かわいらしさや親しみやすさと関係が薄い例もありますが、建築物の場合、日本人の「もったいない精神」に由来していると考えられています。
白銀比は貴金属比のなかでも比較的正方形に近い比率です。木造建築を作る際、角材を無駄なく切り出すために正方形に近い比率が好まれ、結果として白銀比が採用されたという説があります。
白銀比以外の貴金属比
貴金属比とは、デザインに取り入れることで安定した印象を生み出せる比率全般を指す言葉です。貴金属比には、白銀比以外にもさまざまな比率があります。
ここでは、白銀比以外の貴金属比について解説するため、白銀比の理解を深める参考にしてください。
黄金比
黄金比とは、貴金属比のなかでも人間がもっとも美しく感じると言われている比率です。白銀比と比べるとスタイリッシュに見えます。比率は約1:1.618(5:8)です。
黄金比は世界的に幅広く採用されており、世界の歴史的建造物や美術品などにも採用されています。黄金比が採用されている例を見てみましょう。
- 凱旋門(パリ)
- パルテノン神殿(ギリシャ)
- ミロのヴィーナス(彫刻)
- モナリザ(絵画)
- 富嶽三十六景・神奈川沖浪裏(絵画)
- 名刺全般
例を見ると、美術品から日用品まで、黄金比が幅広く活用されていることが分かります。
青銅比
青銅比は第3貴金属比とも呼ばれており、黄金比・白銀比に次ぐ3番目の貴金属比です。白銀比や黄金比と比較すると認知度が低く、デザインに採用されるケースはほとんどないと言われています。青銅比の比率は、約1:3.303(3:9)です。
使用例はあまりないものの、ウェブサイトのメイン画像のサイズを決める際に使われることもあります。白銀比や黄金比以外を使って安定感のあるデザインを施したい場合には、選択肢のひとつとして考えてもよいでしょう。
白金比
白金比は、プラチナ比とも呼ばれている比率です。名前は白銀比や黄金比に似ているものの、厳密には貴金属比には分類されていません。比率は約1:1.732(4:7)です。この数値は、正三角形の底辺の1/2と高さの比に等しいとされています。
青銅比と同様、白銀比・黄金比のようにデザインに多用されることはありません。ただし、比率が正三角形にもとづいていることから、正三角形・正六角形のデザインや複数の要素の配置に役立つと言われています。
白銀比について知れる本
白銀比について理解を深めるためには、本を読むこともひとつの方法です。ここでは、白銀比について解説している本を紹介します。「白銀比についてさらに詳しく知りたい」という方は、記事を参考に本を手に取ってみてくださいね。
法隆寺にひそむ白銀比 五稜郭にひそむ黄金比
江藤 邦彦さんの著書です。数学的な観点から白銀比について解説しています。数学書でありながら、身近に潜んでいる比率や図形について楽しみながら理解を深められる一冊です。
法隆寺の白銀比や五稜郭の黄金比だけでなく、旅先で出会ったさまざまな図形についても触れています。白銀比そのものだけでなく、ほかの比率と比較しながら考えたい方におすすめです。
デザインのための数学
牟田 淳さんの著書で、白銀比の仕組みや理由について分かりやすく学べる一冊です。
大学の教科書をベースに、比較的やさしく書かれており、タイトルには「数学」とあるものの、数学の専門知識などはなくても読めます。また、写真や図も多く取り入れられているため読みやすく、白銀比・黄金比を学ぶ入門書としておすすめです。
白銀比を知りデザインなどに活かそう
白銀比は、特に日本人に好まれ、多くのデザインに多用されてきた比率です。法隆寺や伊勢神宮、東京スカイツリーなど、新旧問わずさまざまな建築物に使われてきました。
スタイリッシュな黄金比と比べて、かわいらしさや親しみやすさを感じさせる比率です。そのため、建築物だけでなく、日本の老若男女に愛される国民的キャラクターにも白銀比が使われています。
白銀比についての理解を深め、デザインなどに取り入れるには、数学的・デザイン的など幅広い観点から見ることが必要です。白銀比をより専門的に学びたい場合は、本から知識を吸収するとよいでしょう。